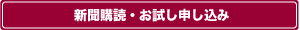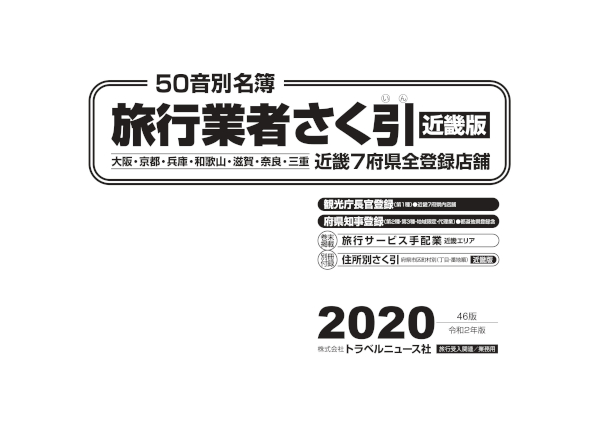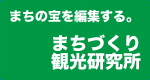観光、移動の視点で考える二次交通 近畿運輸局がシンポジウム
観光による地域活性化を目指す中で、地方で課題に挙がるのが二次交通。地域の特性を活かした観光地域づくりに向けて、観光の視点と交通の視点から二次交通の確保と充実を考える意欲的なシンポジウムが6月7日、大阪市内で開かれた。
公共交通を手段に目的づくり
シンポジウムは「観光による地域活性化と二次交通を考える」と題し、近畿運輸局(日笠弥三郎局長)が主催した。日笠局長は「交通と観光振興を一体的進めることが持続可能な観光地域づくりの一助になる」と開催趣旨を話した。
はじめに、地方の公共交通政策などを専門としている大分大学の大井尚司教授が「観光と日常交通は切っても切れない」関係と切り出し、基調講演を行った。
大井教授は、観光地と知られる島根県津和野町で民間タクシー会社がドライバーと利用者減で廃業し3セクで維持していること、大分県別府市では運行情報が錯綜し観光客が路線バスを利用しづらいことを紹介。一方で、熊本県の九州産交が長距離バスから路線バスや旅館の送迎までを駆使したアナログMaaS、鹿児島交通が行っている多言語表記で路線バスの組み合わせをユニバーサル化したプランを成功事例として伝え、「観光客がどう動くか、動きたいのかという観光客の視点に立つことが大切」と、日常交通と観光移動の融合について話した。
その上で、観光客の視点に立ち公共交通を手段として「こう動くと楽しいという目的づくりを仕掛けよう」とし、観光目的から逆流して二次交通を考えるべきだと呼びかけた。
続いて講演したリクルートじゃらんリサーチセンターセンターの沢登次彦センター長は「一番の課題は二次交通網が可視化できていないこと。行ったはいいが、帰ってこられないかもと不安にさせています。結果、観光消費の機会を損失することにもなります。地域全体で、交通空白地域と時間を埋める作業をしなければなりません」などと話し、地域で二次交通のあり方を検討する当事者間の関係性の質を上げる必要性を説いた。
パネルディスカッションでは、兵庫県豊岡市の全但バスの小坂祐司さんが「地方の公共交通はJR、バス、タクシーと単体で考えるのではなく、地域全体でどう考えるかが大事」、JR西日本和歌山支社の御堂直樹さんも白浜温泉で複数社が連携し運行したオンデマンドバスについて「ローカルな場所では競合するよりも共感・協業する方がいい。お客さんが便利になる手段を構築して、お客さんに交通手段を選んでもらえる環境をつくろうと一致しました」「JRを降りてその先の移動手段がなかったら、お客さんは二度と白浜温泉に来なくなるという危機感もありました。これらの事例についてコーディネーターを務めた大井教授は「地域の課題を交通移動側が気づいた」と評価した。

観光地域づくりをテーマに意見交換
また、二次交通を維持するための担い手が不足している課題について各氏の発言を受けて大井教授は「地域の人、資源、来訪者の満足度を上げるのは観光や移動。その質が上がれば地域に自信が持てて人が来て、住み、働くの好循環が生まれるのではないか」とした。
- 修旅目的地の魅力 長野県学習旅行誘致推進協、近畿圏の中学校教諭ら招く(25/10/31)
- 旅行の価値は良質な「眠り」にあり 楽天がビジネスイベント、睡眠が作る満足度を提言(25/09/03)
- 最新データとトレンド じゃらんリサーチセンター、観光振興セミナー開催(25/09/02)
- 奥能登の今を訪ねて(2) 新たな景観と文化財再建の課題(25/08/04)
- 奥能登の今を訪ねて(1) 被災地の現状と観光の可能性(25/08/04)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(2) テーマは「永遠」2千年前の石など展示/イスラエル(25/05/30)
- 一般来場者数300万人突破・万博会場でナショナルデー(1) 観光名誉広報大使に坂口健太郎さん/韓国(25/05/30)