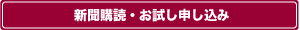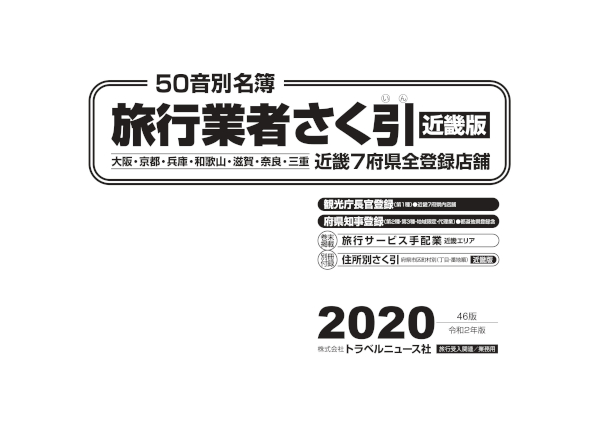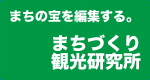“民の力”で迎えた市制100年・北海道小樽市(2) 迫俊哉市長に聞く−歴史と海と港でまちづくり
2030年新幹線開業見据え 量から質の観光へ転換図る
−7月9日に「ぱしふぃっくびいなす」が寄港しますね。
迫 2年10カ月ぶりのクルーズ船の寄港で非常に期待しています。後志管内全体でクルーズ客を取り込み、特に余市町や仁木町は若い町長がワイナリーの誘致など一所懸命にまちづくりに取り組んでいますから、管内全体の底上げにもつながります。小樽もしっかり見ていただきたいですね。
それはフェリーも一緒です。新日本海フェリー(小樽−舞鶴、小樽−新潟)は毎日運航です。フェリー客にも小樽を見て、食べて、本来はその次に泊まるがあるのですが、今までは見て食べての通過型観光といわれておりました。星野リゾートやサンケイグループが進出するなど宿泊のキャパも増えてきているので、見て食べて泊まっての3点セットで底上げを図らないといけません。いかに滞在してもらって、いかに消費してもらうかという量から質の観光に転換していかないと、経済にどのくらいの効果があるのか把握できません。年間700万、800万人来ているだけで本当の意味での観光都市とは言い切れません。
2030年には北海道新幹線が札幌まで延伸されます。新幹線をどう観光振興につなげるか。札幌駅が隣で、ニセコを背後に持つ倶知安駅も隣です。両駅から12−13分が(仮称)新小樽駅ですから、通過駅として本当に埋没しかねません。その中で存在感を示すためにはフェリーと新幹線、クルーズと新幹線を小樽ならではの旅行プランとして造り、フェリーで来た人が新幹線で帰る、逆もまたしかりです。新幹線が来るまでに、クルーズやフェリーとの関係を戦略的に考えないといけないと思っています。フェリーはまさに現代の北前船ですから。
−小樽市観光のイメージリーダーとして歴史的建造物群や運河とともにガラスもあります。
迫 ガラスは漁業の浮き玉を製造することから始まった小樽の伝統的な産業です。北一硝子の浅原健藏さんがガラスのランプを販売し、それが当時の“カニ族”の人気を集め一大ブームになりました。その後、浅原さんは木骨石造倉庫を買われて店舗展開され、歴史的建造物を使った成功事例の第一号でした。一方で芸術家として淺原千代治さんがいらっしゃいます。大阪から移住され、スタジオガラスという吹きガラスの体験を観光客にしてもらい小樽のガラスをPRしていきました。かつて私が産業振興課長時代には手宮線跡を使って「小樽がらす市」も始めました。そういう基盤があり現在は土産物が主になりましたが、小樽にとって代表的な産業であることに変わりません。小学校6年生による卒業記念ガラス製作体験を何年も続けています。

市街地に残る旧手宮線跡。
がらす市の舞台でもある
−小樽観光の伸びしろは非常に大きいですね。
迫 この春には、ニトリが新しく倉庫を購入し西洋美術館をオープンしました。これからも民の力で観光まちづくりが進んでいくように、民間が小樽に投資をしようと思っていただけるコンセプトを打ち出し共感いただかなければなりません。この先100年も市民と一緒にまちづくりを継続していきます。
(次の記事)“民の力”で迎えた市制100年・北海道小樽市(3) 「小樽ガラス」が紡ぐ歴史と未来−シンポジウム1
(前の記事)“民の力”で迎えた市制100年・北海道小樽市(1) 迫俊哉市長に聞く−「北の商都」で日本遺産目指す
- 【観光業界リーダー年頭所感】日旅西日本スクラム会 会長 下平晃寿 氏(26/01/18)
- 【観光業界リーダー年頭所感】近畿日本ツーリスト旅丸会 会長 吉田瑛 氏(26/01/18)
- 【観光業界リーダー年頭所感】日本旅館協定旅館ホテル連盟 関西支部連合会会長 金子博美 氏(26/01/17)
- 【観光業界リーダー年頭所感】JTB協定旅館ホテル連盟西日本支部連合会 会長 岸本一郎 氏(26/01/17)
- 【観光業界リーダー年頭所感】JTB協定旅館ホテル連盟 会長 宮﨑光彦 氏(26/01/17)
- 【観光業界リーダー年頭所感】一般社団法人全日本ホテル連盟 会長 清水嗣能 氏(26/01/16)
- 【観光業界リーダー年頭所感】全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 シルバースター部会長 伊藤隆司 氏(26/01/16)