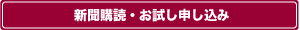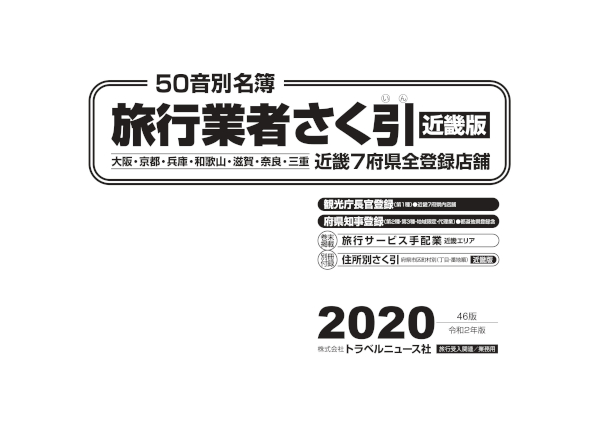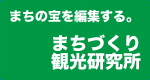新型コロナウイルスと観光業界 特別寄稿・松坂健さん「『禍』転じて今、我々がすべきこと」(5) ワーケーションの本質
(4)変な英語に惑わされるな。
マイクロツーリズム、ワーケーション、ステイケーション。変な外国用語が流布しはじめて、なんだかこそばゆい。
言ってる中身は理解できなくもないし、みんな大事なことなのだけれど、こういう風にキャッチフレーズ化すると、それらがみんな「風俗」化して、意味内容の重みが失われていくような気がしてならない。それを唱えていればなんとかなるみたいな護符というか呪文というか。
マイクロツーリズムって、これまで言われてきた着地型ツーリズムとどこが違うの? と言いたくなるし、近郊の方々の顧客化なんて、いまさらいわれなくてもそれはマーチャントの鉄則でしょう、とまぜっかえしたくなるのは僕の悪い癖だ。
リモートワークがこれほど進むとは正直思っていなかったので、これはリゾートにも良い影響が出ると喜んでいる。
そこでワーケーションだよ。ワークとバケーションを両立させる? こういう風にワークと休暇を分けるから、「両立」という発想になる。
僕はワークとバケーションの「融合」と言いたい。融合だから、仕事は完璧に、定時に囚われずに自由にやりたいし、ふと魚釣りに出掛けたくなれば渓流があるし、簡単な山登りだってできる。町の中央のカフェには様々な業種の人たちが集まるので時に有益な情報も得られる。そういうのが僕の「融合」の意味で、言ってみれば「ロッキーの大自然とマンハッタンの都会性の融合」ってことになる。
それがワーケーションなんて言葉に集約されてしまうと、旅館さんのお部屋の一部をOAルームにしました、なんてきわめて戦術的レベルの話に終わって、カスタマーへの「驚き」にならなくなってしまう。
もしかしたら、この問題こそ、温泉リゾート全体で取り組む課題でないか。たとえばキンコーズのようなショップが町にほしい。ワークは終わりまで「完結」させるところに意義がある。旅館さん、せめてプリンタのいいのを装備してくだされ。これまで、USBなどを持ってロビーにあるプリンタで打ち出せたホテルはアメリカ・マリオットのチェーンホテルだけだったなあ。
なにはともあれ、新用語のまん延、その呪文効果をまともに受けとめないように。
(松坂健=元跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授)
(次の記事)新型コロナウイルスと観光業界 特別寄稿・松坂健さん「『禍』転じて今、我々がすべきこと」(6) 従来の成功体験を捨てた「驚き」
(前の記事)新型コロナウイルスと観光業界 特別寄稿・松坂健さん「『禍』転じて今、我々がすべきこと」(4) 刹那快楽消費を見極める
- 27年「ベオグラード万博」をPR セルビア政府観光局・マリヤ・ラボヴィッチ局長(25/10/17)
- いよいよ開幕「大阪・関西万博」(4) 空飛ぶクルマが離発着/大阪メトロ(25/04/14)
- いよいよ開幕「大阪・関西万博」(3) 自然や文化、伝承―地域の個性を発信/関西9府県パビリオン(25/04/14)
- いよいよ開幕「大阪・関西万博」(2) 25年後の自分と出会う/大阪館(25/04/14)
- いよいよ開幕「大阪・関西万博」(1) いのち輝くを実感/シグネチャーパビリオン(25/04/14)
- 誰もが旅を楽しめる兵庫県(4) ひょうごユニバーサルな観光地(25/03/31)
- 誰もが旅を楽しめる兵庫県(3) ひょうごユニバーサルなお宿(25/03/31)