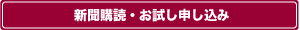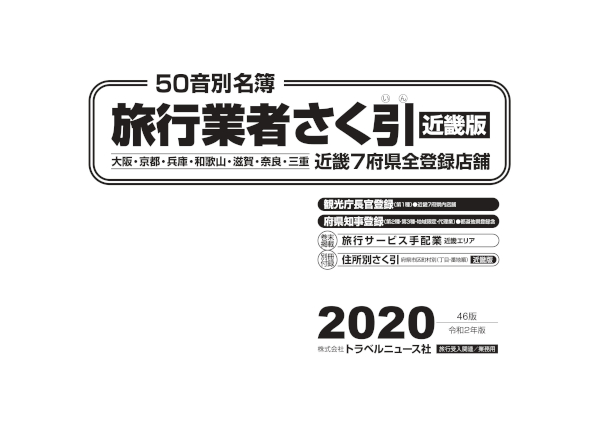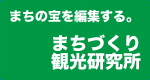嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(2) まちづくりの戦略/佐賀嬉野特集
百カ所の魅力的な場づくり 地域全体で顧客を維持する
−コロナ禍では観光の構造自体が大きく変わりました。
山田 今はいろいろなテーマのツーリズムがあり、例えばウェルネスツーリズムはコロナ禍で注目されました。でも、ただ健康になりたいだけでは東京都内にいくらでも関係施設はあります。
村上 むしろ、そっちの方が多い。
山田 わざわざ健康になるためにどこかまで行くか、ということですね。その意味では、今後はさらにリアルな価値が重要です。サービス内容や商品力の付加価値が高くないとお客様から選ばれなくなることははっきりしている。コロナの対応だけではなくて、今の人口減少社会では、どちらの課題解決に対しても戦略は同じです。要は市場が縮小していくわけですから。コロナ禍の場合は団体で密にということができなくなり、客数や販売数を増やすことができなくなってきています。つまり量より質の転換を図る時に、高付加価値の商品やサービスにシフトしていかないと、お客様が嬉野に来る理由や価値、必然性にまったくつながりません。
人口減、少子化、高齢化の中の市場の変化をコロナが後押しした結果、さらに個人化・多様化していく市場に対して迅速にコミットしないといけません。量から質へという高付加価値を図ると同時にリテンション戦略として顧客維持、つかんだ客を離さないこと。これに関してはいろんな宿や事業者が個々にやってきましたが、今後は嬉野市で取り組むことが必要となります。一度来ていただいたお客様をつかんで離さず何度も来てもらうようにするか、要はお客様から生涯価値を見い出すことを考える。そこが一番大きなポイントになると思います。
村上 これまで集客の常套手段はイベントでしたが、密が密を呼ぶ時代ではなくなりました。むしろ密の状況では観光客が避けるという発想に変えなくてはいけません。そうなると1カ所に5万人を集めるのではなく、例えば100カ所に500人ずつ集めて5万人という、掛け算の経済効果を上げていかないとダメかなと思っています。
実は、ここのお隣では酪農家が「牛乳出しコーヒー」というミルクブリューのお店を出して、それを目がけて若い人たちが塩田津を歩き始めるという現象が起きています。そういう今あるものを磨き上げて魅力的な場所を100カ所、200カ所つくる。そこを巡ることがリテンション戦略にも関わり、1日で100カ所を回り切れるわけではないので次はあそこに行ってみようと、地域全体が魅力的な場所だと認識いただければ、リピートにつながるのではないかと思います。
今、嬉野市だけではなく積極的に近隣市町と連携を進めています。鹿島市と太良町という枠組みと、同世代の首長がいる武雄市と有田町との関係を住民に還元しようと、まずは観光面で連携しています。職員が一緒に研修を受けたり、若手職員でサイクリングコースを3市町で設定することなどを行い交流を深めています。有田町にとっては嬉野市に泊まって窯元に来てもらう、武雄市は嬉野にないものを持っている。その組み合わせを商品にしていこうと考えています。新幹線が開業し隣駅同士で喧嘩する絵図が思い浮かびそうですが、武雄イン嬉野アウトでも、その逆でもいい。そんな周遊プランを3市町でつくっていこうと考えています。
山田 いま市長が言ったことはとても大事です。北陸新幹線ができる前に富山県から依頼がありました。終着駅効果で金沢に観光客を奪われないように、富山県内の3つの駅で途中下車してでもほしくなる魅力ある価値のある商品を企画するためのセミナーの依頼を受けました。
でも、それは違う。魅力ある商品を造り続けられる人材を育成しないと、単発で終わってしまう可能性が高くなる。経営能力を高める人材育成をしないとダメなのではないかと。私以外にもいろいろな先生に参画いただきカリキュラムを作りました。2年、3年後ぐらいから卒塾生と塾生の連携や卒塾生が教える側にまわり、自分たちだからこそできる教育体制ができてきました。誰かから教わらないといけないし、学び合わないといけないという体制をつくると継続していきます。新幹線の開業効果は初年度、石川県、金沢がぐっと伸びましたが、国内宿泊客でその後に伸びたのは富山県だけです。
和歌山大学との連携も継続した人材育成を仕組みとして定着させる。地元の経営力が育つことによって、今までできなかったことができるようになる。1が頑張ることによって1・1、1・2になると掛け算によってどんどん増えていくわけです。経営能力がなくて1未満だと掛け算しても増えない。頑張って1・1以上になると、自ずとうまく回っていきます。
富山県がうまくいったのは、観光塾以外に起業塾が別にあり、就農者を増やす農業カレッジもあったのですが、私からマネジメント講義だけは三塾連携のプログラムにしようと提案しました。その結果、今まで畑違いの人たちが共通言語化とネットワークから新しい動きが始まりました。
嬉野市の場合も、今は観光関連や商業の人たち、お茶の生産者もいますが、もっといろんな産業からいろんな人たちが関わり人材育成ができれば広がりが出てきます。その広がりとともに、提供される商品やサービスの内容が深くなり、価値が高まる相乗効果が期待できます。私の経験則としても確信していることもあり、将来的には同じような姿に持っていけるといいと思っています。
(次の記事)嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(3) 人づくりの要諦/佐賀嬉野特集
(前の記事)嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(1) コロナ禍のあと/佐賀嬉野特集
- 嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(5) 2030年の嬉野市/佐賀嬉野特集(21/12/15)
- 嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(4) 仮説を立てる/佐賀嬉野特集(21/12/15)
- 嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(3) 人づくりの要諦/佐賀嬉野特集(21/12/15)
- 嬉野市が射程するまちづくり 村上大祐市長VS山田桂一郎氏対談(1) コロナ禍のあと/佐賀嬉野特集(21/12/15)
- 美肌の湯、茶、焼き物− 嬉野市の魅力/佐賀嬉野特集(21/12/14)
- 和歌山大学観光学部と連携 うれしの未来づくり塾、まちづくり担う人材育成/佐賀嬉野特集(21/12/14)
- 90年ぶり鉄路復活 西九州新幹線・嬉野温泉駅、観光拠点化進む/佐賀嬉野特集(21/12/14)