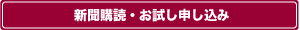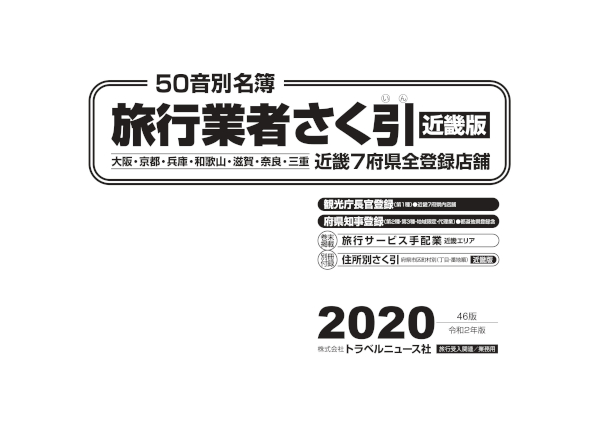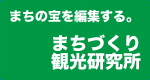インバウンドと富裕層
「インバウンド」と「富裕層」。地方自治体の首長が観光について話す時、この2つのキーワードを耳にすることが多い。円安もあって外貨獲得の有効策はインバウンドだし、地方創生を進める上で消費額が多い富裕層を呼び込もうとするのは間違っていない。
やや古いデータだが、日本政府観光局によると2024年6月の訪日外国人旅行者数は313万5600人で、単月としては過去最高を記録した。今年1―9月の訪日外国人の消費額は5兆8582億円で過去最高を記録し、これは23年年度の年間消費額を上回った。この数字を見えれば、富裕層のインバウンドに来てもらえれば多額のお金が落ち地域経済が活性化すると思うのは当然だ。
ただ、日本の観光客数の全体からするとインバウンドが占める比率は17%。このうち富裕層となるとさらに比率は下がるだろう。ある旅館経営者は「この17%が日本各地の宿泊施設や観光地を潤してくれるのか。インバウンドが悪いというわけではない。もっと全方位を見て観光客の誘致活動をしなくてはいけない」と指摘する。
本紙コラム「NATO廃絶」の通り、量から質への転換、薄利多売からの脱却は必要不可欠だ。そのためインバウンド、富裕層を誘致し高収益を得るということだろうが、もう一つの最近のキーワードに「多様性」がある。皆が同じ指向だと“没個性”に陥り、地方が“陳腐化”しインバウンドバブルが弾けないか…。
(トラベルニュースat 24年10月25日号)
- “便乗員“より添乗員(25/12/12)
- 地元商店と一緒に誘客(25/11/27)
- 車窓越しの交流で集客(25/11/13)
- 町の本屋さんから学ぶ(25/10/28)
- リアリティが名作を生む(25/10/14)
- 万博会場で示した決意(25/09/26)
- 動いてナンボが観光人(25/09/12)