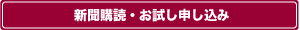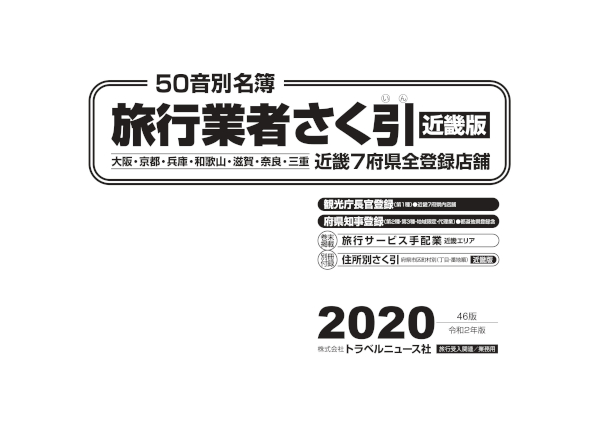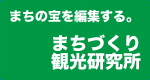新クルーズ学コラム

備後商船の新造船 尾道—常石ミニクルーズ
広島県の尾道は、本州側と向島側の両方の小高い山に挟まれた尾道水道と呼ばれる狭い水道に面した港町で、四国の今治まで島づたいに橋でつながる「しまなみ海道」の本州側の基点ともなっています。放浪記で有名な林芙美子が青春時代を過ごした地としても有名で...

フェリーきょうと登場 ワンナイトクルーズの旅
また瀬戸内海に新しい大型フェリーが登場しました。船名は「フェリーきょうと」で、運航するのは名門大洋フェリー。総トン数は1万5400トンで、全長195メートル、幅27・8メートルの大きさで、船内には全通する2層の車両甲板と、その上に3層の旅客...

与論島ワンデイクルーズ やんばる遠望し美ら海を航行
縄が本土復帰する前、鹿児島県最南端の離島である与論島は若者にとって憧れの島で、1970年代の離島ブーム時には年間20万人もの観光客が訪れたといいます。その後、観光客数は漸減して平成24年の5万人がボトムとなり、その後増加に転じて今は7万人に...

フェリーを使った修学旅行 SDGsや社会見学の学び
北海道の港町室蘭で育った私の中学の修学旅行は、列車と青函連絡船を使った仙台と松島への旅でした。そのころは北海道を出る旅はほとんどがこのルートで、長時間の列車が当たり前でした。今では北海道への人流の86%は飛行機となり、続いてフェリー8%、鉄...

日本の遊覧船事業 コロナ禍で打撃も様々な工夫
「クルーズ客船に乗りたいですか」と聞いたアンケートに、日本人の約50%の人が「船酔いが嫌なので乗りたくない」と答えたといいます。すなわち日本人の約半分が、船酔いを恐れて船に拒否反応を示していることになります。 たしかに、「板子一枚下は...

新日本海フェリー「はまなす」に乗船 船で行く夏の北海道
関西から北海道にでかけるには飛行機の利用が一般的ですが船で行く方法もあります。 日本海側の舞鶴からは小樽に、敦賀からは苫小牧に、新日本海フェリーのカーフェリーが毎日それぞれ1便就航しています。しかも、出港は深夜なので、仕事を終えてから...

茨城県取手市「小堀の渡し」 住民の足から観光の目玉に
かつて全国の川には渡し船がありました。しかし、次第に多くの川に橋が掛けられて、渡船の利用客は減少して、やがて渡し船が姿を消したところがほとんどです。そうした中で、珍しく市営の渡船が新造されたと聞いてでかけてみました。 茨城県の取手市営...

Go Toフェリー 船旅満喫できる志布志航路
本格的なクルーズには行きにくい状況が続いているので、主にフェリーでの船旅を楽しんでいます。今回はフェリーとホテルがコラボしたツアーを紹介します。 日本では300キロメートル以上の航路に就航するカーフェリーを長距離フェリーと呼んでおり、...

世界遺産・五島列島の島めぐり
九州・長崎県の五島列島の島々は隠れキリシタンの島として有名で、教会を中心とするいくつかの集落が「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界文化遺産に認定されています。五島という島はなく、中通島、若松島、奈留島、久賀島、福江島の5つの...

宇和海で楽しむ春の船旅
前回はGo Toフェリーと題して、宿泊設備があって1泊の船旅の楽しめるフェリーについて書きましたが、今回はもっと手軽に楽しめるクルーズを紹介します。 桜の季節になり各地のお花見船が賑わっています。また琵琶湖も海開きとなってレストラン船...