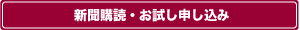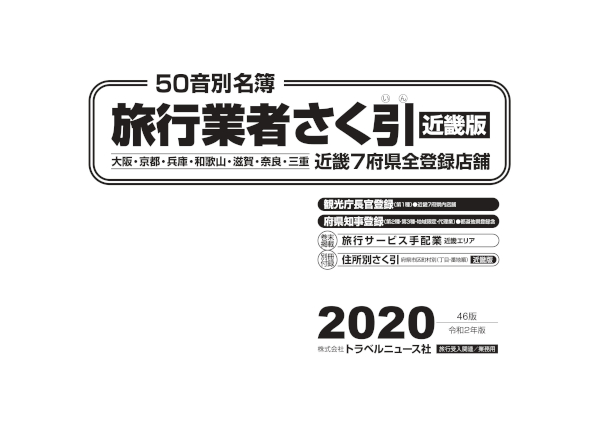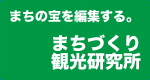旅する講談コラム

講釈師が語る黒雲の辰その六 積悪の報いも老中の印が押されず
「或遭王難苦、腹減った、臨刑欲寿終、飯食うで、念彼観音力、もう寝るわ、刀尋段々壊」女房の方も糸車を取る手で「或遭王難苦、臨刑欲寿終、念彼観音力、刀尋段々壊」とやっておりますから、二人は村人より「とうじんだんだんねの夫婦じゃ」とあだ名されるよ...

講釈師が語る黒雲の辰その五 お辰の無事願うお経の教え乞う
「どうせいつかは仕置きの上、野末の晒し首、其の時に可哀想だ、気の毒だと言ってくれる者は誰もいやしないだろう。黒雲の辰が仕置きに上がったと噂に聞けば、あの女は身の浮き橋を踏み外し、とうとう地獄に落ちたかとお経の一つ、折れた線香の一本でも手向け...

講釈師が語る黒雲の辰その四 七十五両が八十五両に増え戻る
「喜びな、お爺さんの命は助かった」言いながら懐より次から次へ「此の財布には十両も入っているはず、おや十一両、豪気なもんだね、こっちの紙入れは七両二分、これは巾着で五両一朱、こっちはバカに軽いね。たったの二百文。これは講釈師の財布だ。紋付(羽...

講釈師が語る黒雲の辰その三 信兵衛、川から女に救われる
「待ちな」と鋭い一声、振り返れば、矢筈飛白(やはずがすり)の衣類、爽やかな帯、御守殿(ごしゅでん)風に着こなしたお屋敷勤めと思しき女が一人 「助けると思うて死なしとくなはれ」「何を無茶なことを。待ちなと言えば待ちな」「どう仕様もないん...

講釈師が語る黒雲の辰その二 信兵衛、御用金をいかれてしまう
ただもう嬉しさのあまり、後先の分別もなく出立の用意に及びまして、七十五両の大金を胴巻に、これから夜を日に継いで江戸へ到着、本所横網の三河屋と言う宿屋に泊まります。 「やっと江戸に着いた、講談やからこんなに短いけど、ほんまは二十日間くら...

講釈師が語る黒雲の辰その一 正直者の信兵衛、江戸に向かう
時は享保の五年、処は大和国添下郡、真木坂より一里半程隔った所に黒木村、此処は江戸の小石川鷹匠町にお屋敷を構えておいでになる旗本、黒木大和守のご領地。誠に気の良いお殿様で、日照り続きの不作の年には無理に年貢を取らず自らの屋財家財で売り食いをす...

講釈師が語る円山応挙その九 太夫、絵姿になって親を救う
「それで、その娘さんは。随分昔に攫われた」「ええ。そうだす。ワテら夫婦は、元大坂の天満の天神さんの辺りに住んでおりました。おみつと言う娘が一人居てましたな。其のころはわしらも必死に働いてまして、おみつも寂しい思いをさせてましたんやろな、遊ん...

講釈師が語る円山応挙その八 幽霊の全盛期?綺麗な女子画
「へぇおおきに。これもなぁ。皆先生のお蔭やと思うて。喜んでおりますねん。あの掛け軸の画。掛けた途端、お客さんがどんどんと来てくれはりましてなぁ。店も新しいなって、ご贔屓からそれやったら屋号も新しくしようか言うて、海老芋と棒鱈の文字をとって『...

講釈師が語る円山応挙その七 幽霊の画で甚兵衛の店賑わう
「じいさん、一本つけてんか?」「あぁおいでやす、どうぞ奥へ」「あぁどうもじいさんとこもなぁ。ここんところ御無沙汰してしもうたけども、何やこの店えらい陰気になってしもうたな。あぁおおきに。それからなんぞつまむモンも持って来てんか。あの海老芋と...

講釈師が語る円山応挙その六 思わず生まれた足がない幽霊
散々に迷った挙句。思い切って人の気を引く絵を描いてみようというので、得意の幽霊画を描くことにいたします。夜になるのを待ち受けてまして、わざと行燈の火も薄暗くして筆をとり始め、ふと思い出しましたのが、かつて長崎の巴楼で描いた髪をおどろに振り乱...