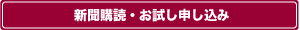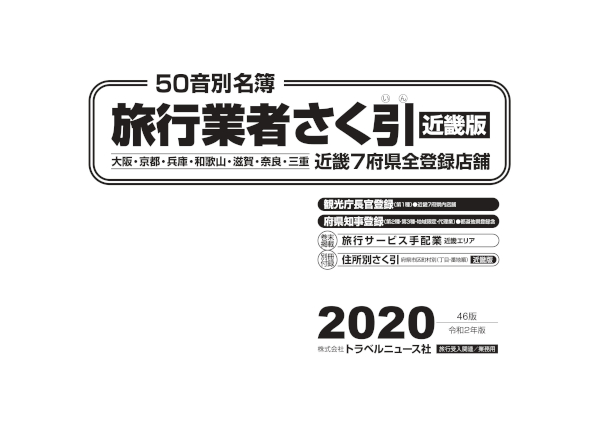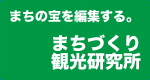「会話と対話の違い」を考える
心のバリアフリーが推進され、共生社会を実現することを目指している今も障害のある人はかわいそうであり、一方的に助けられるべき存在といった誤った理解がなされていることがある。障害の有無にかかわらず、すべての人が助け合い、共に生きていく社会を実現するためには、私たちの生活や心の中においても「障害者」という区切りをなくしていく必要があります。
ただ、「会話」ではその誤った理解を正すことは難しい。その過程において、ほんの少しでもズレが生じるのであれば「対話」が必要になります。
「対話」とは、相手と向かい合い、二人きりで話すことですが、なぜ二人で向かい合って話さないといけないのでしょう?
それは、お互いに共通する状況の「意味」を共有するためです。例えば、同じ景色を見ていても、受け取る思いはみんなバラバラです。何か一つかみ合わなくなると、やはりそこにズレが生じ、そのズレを修正していくためには、「会話」ではなく、「対話」が必要になってくるのでしょう。
これが仕事となるともっと厄介です。同じものを見ているのに、なぜそんなふうに捉えるのか理解できない…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2022年11月10日号)
- バリアフルレストラン パートⅠ(25/03/14)
- 「ジェロントロジー(齢創学)」を考える(25/02/14)
- 宿泊業における改正障害者差別解消法(24/12/16)
- サービス介助士25周年~サービス介助士が社会を変える~(24/11/20)
- 大阪・関西万博のテーマを実現するために(24/10/18)
- インクルーシブ防災とは?(24/09/17)
- ケアフィットの認知症オンライサロン(24/07/18)