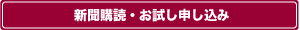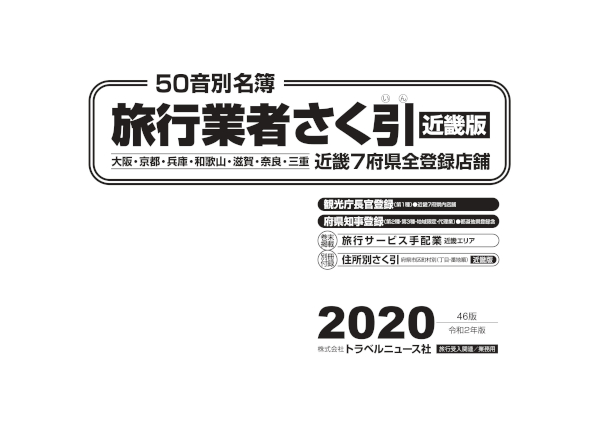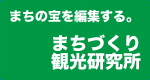共創の旅―サービス介助士日誌コラム

防災介助士の学び
週末をテレビの前でのんびり過ごしていると突然、津波注意報の速報でした。 太平洋岸の広い範囲に津波注意報が出ているが、どこで揺れた? 何が起きた? そんなことを考えていると日本時間の2日午後11時37分ごろフィリピン付近を震源とするマグ...

バリアフルレストラン、ご存知ですか
バリアフルレストランとは、“障害の社会モデル”を体感できる体験学習プログラムで、“チーム誰とも(運営主体は日本ケアフィット共育機構)”が企画実施しています。 “社会が作り出す障害”が何なのかを参加しながらにして理解できるようになってい...

認知症の発症と「難聴」の関係
今、皆さんのパソコンやスマートフォン、またテレビの音量はどうなっていますか? 最大限になっていませんか? 耳を守るための適正音量は、機器が出せる音量の半分以下と言われています。 さて、近ごろ耳の聞こえが悪くなったと感じることがあるなら...

アルツハイマー病治療薬と予防
8月21日、厚生労働省の専門部会は日本のエーザイと米バイオジェンが開発したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の承認を了承しました。アルツハイマー病の進行を緩やかにする効果を証明した薬として国内初となり、認知症治療の大きな一歩と期待が膨らみ...

ヘルプマークって誰が使うの?
最近、ヘルプマークを鞄につけている方をよく見かけるようになりました。小さなお子さんやお元気そうに見える若い世代の方など様々です。そもそもこのマークはどんな方が、どんな意図を持って持たれているのでしょう。また私たちにできることは何だろう?かを...

視覚障害者が怖い!って感じる時
視覚障害といっても障害の程度や見え方も様々です。これまでもお話ししてきたように、視覚障害=見えない人と決めつけてはいけません。 先日、視覚障害のある方々と意見交換をする機会がありました。その際、一番怖い思いをするのは「声かけもなく突然...

旅のUDアドバイザーって?
皆さんは、旅のユニバーサルデザイン(UD)アドバイザーをご存知ですか? 多様な人と多様なサービスを学び、それらを組み合わせることによって、お手伝いが必要なお客様を含め、すべてのお客様の旅の目的を叶えるための資格です。年々増加する高齢者...

合理的配慮とLGBTQ
国会会議場において、性的マイノリティをめぐる議論が活発になっているのを見ながら、いよいよ日本も遅れていた法制化に向けて動き出すのか?と思いきや、G7広島サミットを目前に控えているからだと分かりました。 G7加盟国として唯一性的マイノリ...

合理的配慮の義務化まであと一年
2016年に施行された「障害者差別解消法」が21年に改正され、合理的配慮は、民間事業者に向けての努力義務が法的義務化となることが可決し、公布から3年以内に施行されます。配慮でよかったものをなぜ義務化するのか? 配慮なのだから、思いやりを持て...

手話言語条例
「手話言語」をご存じでしょうか? 手話言語とは、手の形、位置、動きをもとに、表情も活用する独自の文法体系をもった、音声言語と対等な言語で、障害者権利条約の定義に手話が「言語」として位置づけられ、日本においても改正障害者基本法で初めて「...