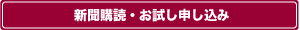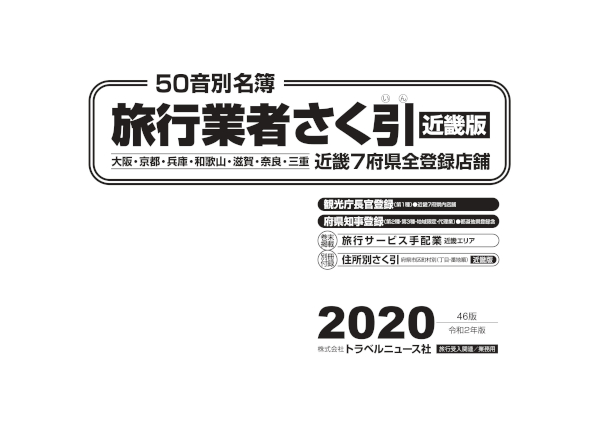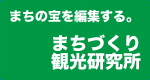共創の旅―サービス介助士日誌コラム

「心のバリアフリー認定制度」がスタート
2020年を機に「共生社会」や「心のバリアフリー」という言葉を様々な場面で見かけるようになりました。そして、観光施設における心のバリアフリー制度として第一弾の66施設が認定されました。ともにバリアフリーに関する教育訓練を実施してきた観光施設...

“認知症”対応の公共交通接遇ガイドライン策定!
国土交通省では、令和元年6月18日に決定した「認知症施策推進大綱」やSDGsの「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現のために、公共交通事業者に向けた接遇ガイドラインにおいても、認知症の人に対する対応の際の留意点をまと...

心のバリアフリー認定制度の創設
バリアフリー法の改正に伴い、観光施設が積極的にバリアフリー対応に取り組んでいることを認定する制度が創設されました。宿泊施設、飲食店、観光案内所などが該当施設です。 認定基準としては、次のことをすべて満たす必要があります。 (1)...

「障害者差別解消法改正法」が成立
「障害者差別解消法」は、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に制定され、16年に施行されました...

「新しい生活様式」が生み出す困りごと2
障害のある人のなかには「新しい生活様式」の必要性が十分に理解できず、自分と周りの人と適切な距離を確保することが難しい方もいます。例えば、知的障害のある方にとってはレジで並ぶ時の立ち位置を把握するのが難しい場合もあります。 人との適切な...

「新しい生活様式」が生み出す困りごと
緊急事態宣言が解除され、喜んだのも束の間、こんなにも急速に第4波が…。感染者数が急激に増えている原因の一つに「変異ウイルス」、そして今「まん延防止等重点措置」の適用。この状況を私たちはどう受け止めるのか、緊急事態宣言のレベルに逆戻りしたと考...

サービス介助士だから気づく防災の視点
緊急事態宣言が一部前倒しで解除されましたが、まだ安心はできません。新型コロナウイルス発生から1年が過ぎ、私たちは何を学んだのでしょう。 1.マスクの着用と手洗いの徹底 2.3密回避 3.ソーシャルディスタンス この3つにプラ...

サービス介助士とは
新しい年も1カ月が過ぎ、緊急事態宣言がまだ解除されない中ではありますが、気持ちだけは前向きに元気にスタートしたいですね。 今回は初心に戻り、あらためて、「サービス介助士」とは何ができる人なのかをお伝えしようと思います。サービス介助士を...

サービス介助士の心構え
2021年も新型コロナウイルスからスタートすることになりそうですが、私たちにできることは徹底した感染防止しかありません。ワクチンが承認されるニュースも多く聞けるようになったものの今は一人ひとりの新しい生活様式を具体化していきましょう。 ...

サービス介助士におけるガイドライン
2019年12月に新型コロナウイルス感染症(COVID―19)が確認され、一年が経過した今も感染が拡大し、収束に至りません。「3密を避ける」対策を取り、「飛沫感染」と「接触感染」をしない「新しい生活様式」を送りながら、また新たな困りごとが発...