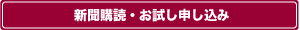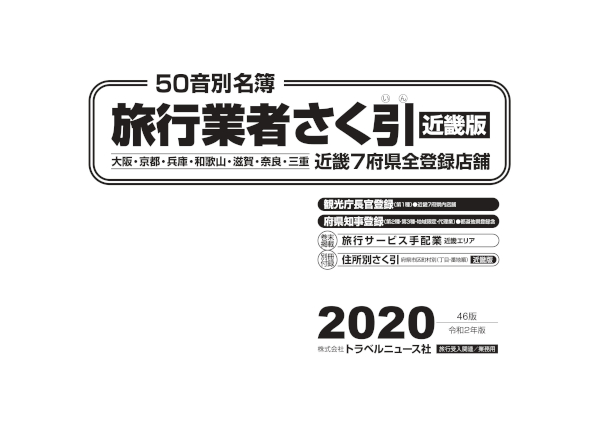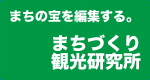共創の旅―サービス介助士日誌コラム

サッカーW杯に学ぶ“バリアのない”観戦
こんなにもサッカー好きな人が世の中にはいるのか?と感じながら、夜中の2時に目覚まし時計をセットし、テレビの前で正座しながら必死に声をからしている人を何人も知っています。残念ながら終了のホイッスル音を聞く寸前にGoal!の声が響く…。 ...

「心のバリアフリー」船舶にも急務
「心のバリアフリー」「ユニバーサルデザイン」「障害の社会モデル」を鉄道、航空、ホテル、旅館など観光産業を舞台に見てきましたが、まだ船舶は覗いていませんでした。 海上交通における船舶については国土交通省がまとめたバリアフリーマニュアルが...

「旅館らしさ」の中でできる心配り
先日、山陰で旅館業を営む方から館内バリアフリー化についてお聞きする機会がありました。 10年以上の時間をかけ、コツコツと小さな努力を続けてきた結果、今の時代に必要とされる旅館ができてきた、お客さまに楽しんでいただけるアイデアはまだまだ...

「心のバリアフリー」を体現するには(3)
「心のバリア」とは何か、そして「心のバリアフリー」とは何か、今回は誰もが生きやすい社会を作っていくために私たちがすべきことを考えていきましょう。 そもそも「心のバリア」とは何でしょうか? それを考えるのに大切なのは「障害の社会モ...

「心のバリアフリー」を体現するには(2)
心のバリアフリー第2弾として、今回は少し架空の世界をイメージしながら「心のバリアフリー」を考えてみましょう。 例えば、社会で生活している8割が車いすを利用しているとしたら、街中の建物はどうなっているでしょうか? 利用者の8割が車...

「心のバリアフリー」を体現するには(1)
今回のテーマは、「心のバリアフリー」です。 2020年東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに社会が変わろうとしています。障害のある人もない人もともに生きる共生社会の実現を目指すこの大会には「ユニバーサルデザイン2020行動計画」...

相手の気持ちに寄り添う必要性
先日、JR天王寺駅で視覚障がい者の駅体験と駅社員との勉強会が実施されました。私たちサービス介助士も参加させていただき、盲導犬ユーザーをはじめ28名の視覚障がい者が一堂に集まる大掛かりな勉強会です。目的は、視覚障がい者に駅の構造を知っていただ...

認知症予防には生活習慣病対策
認知症の大部分は、アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症で占められています。認知症を予防するためには、主にこの2つの疾患への対策が課題となります。 脳血管性認知症は脳梗塞、脳出血が原因となる疾患なので危険因子である高血圧や糖尿病、肥満...

まずは「認知症」とは何かを知る
認知症は病名ではなく脳という身体の一部が病気になった状態であり、加齢により誰にでも起こり得る病気だというところまでお話ししました。 今回は認知症の主な種類とその原因となる疾患についてお話しします。 認知症には引き起こす原因によっ...

「認知症」は老化ではなく病
敬老の日を迎えるころに総務省統計局から、日本の高齢者動向をまとめたレポートが発表されました。それによると65歳以上(高齢者)の人口は2017年9月15日時点で3514万人となり、総人口に占める割合は、27.7%に達しました。まさに超高齢社会...