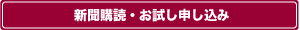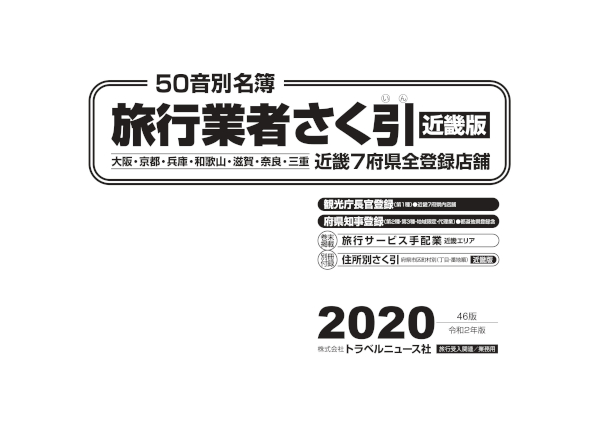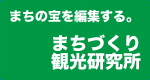中小企業に「越境学習」を
学習方法には「経験学習」と「越境学習」の2種類があります。経験学習とは、その名の通り、同じ環境で経験を深堀していく学習方法。越境学習とは、違う環境に身を置き、固定観念を打破し視野を広げていく学習方法です。
現代において、学校でも職場でも、越境学習のできる人材がより成長し、イノベーションを起こす原動力になっているように思えます。しかし、越境学習することの裏返しには、現在の職場の人手が減ってしまうので、人を減らせない現場では越境学習は難しいのも確かです。
しかし、内部留保や人材が豊富な大企業と、ぎりぎりの人数で経営をしている中小企業で、差が生まれ始めています。人を出せる民間企業と、人を出せない行政でも差が出つつあります。それは越境学習ができるかできないかの差です。越境学習のできる民間大企業は、外に出て成長した人材によるイノベーションが進み、経験学習しかできない企業・組織からは人材が流出するだけで人手不足に陥っている。そんな気がします。
ただし、似たような風土の組織でジェネラリストとして一定期間働く出向は越境学習とは違います。越境学習とはあくまで異文化の中でスペシャリストとして活躍することです。徳島県のクラフトビール工場で醸造に関わっていたのは有名商社や広告会社の若手社員さんでした。それぞれが新人社員として、ゼロから自分自身の調達や企画の知識の応用について実践的に学び、新たな自社のイノベーションに挑戦していくことが越境学習の目的です…
(井門隆夫=國學院大學観光まちづくり学部教授)
(トラベルニュースat 2024年3月25日号)
- 「不安」を旅行需要に転換(26/01/06)
- 同調圧力のない面倒な旅のススメ(25/12/01)
- リアルな救いの場づくりが役目(25/10/29)
- 代打・菅澤“若者よ地球で遊べ”(25/09/29)
- 60の壁と知恵と「怪獣の花唄」(25/09/01)
- マルハラで病むなら旅に出よう(25/07/29)
- 生成AIにできない雑談の創造力(25/06/26)